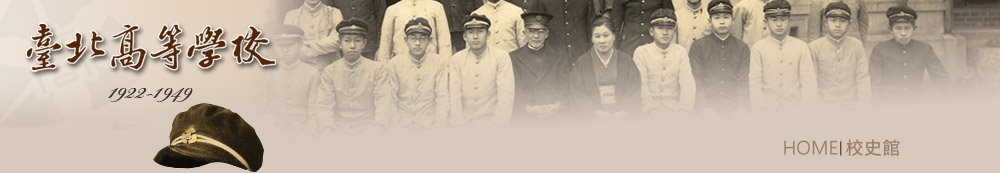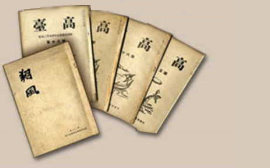台北高等學校年表
| 1922 | |||
| 2~4. | 「台湾教育令」「台湾総督府高等学校官制」等の法令が次々に公布される | ||
| 4.23 | 「台湾総督府高等学校」開校式並びに尋常科第一回入学式挙行。校舎は台北ー中の一隅を借り、本初の七年制高校の一つとなる。初代校長は台北ー中の松村傳。明治時代の代表的洋画家・塩月善吉(塩月桃甫)が図画科教師として就任 | ||
| 1925(大正14年) | |||
| 5.4 | 高等科第一回入学式。明治時代後期に博物学者及び人文学者として有名になる鹿野忠雄が入学 | ||
| 5.26 | 学生たちの自由を守るため、文教局と掛け合った教育家三澤糾が第二代校長に就任 | ||
| 6. | 「学友会」15部を開設 | ||
| 1926(大正15年) | |||
| 3.5 | 学友会雑誌『翔風』創刊 | ||
| 3.20 | 「普通教室」(現普字楼)竣工 | ||
| 3.31 | 「生徒控所」(現文薈庁)竣工 | ||
| 4.25 | 今の古亭本部校舎に移転 | ||
| 9.10 | 初の「観月舟行」を挙行。「観月舟行の賦」を創作 | ||
| 1927(昭和2年) | |||
| 5.10 | 「理化教室」(現存せず)竣工 | ||
| 5.13 | 学校名を「台湾総督府台北高等学校」に改称 | ||
| 1928(昭和3年) | |||
| 11.9 | 「本館」(現行政大楼)竣工 | ||
| 11.15 | 第一回「記念祭」挙行。「生蕃踊り」(後の高砂踊り)初披露。演劇初公演 | ||
| 12.27 | 「体育館」(現存せず)竣工 | ||
| 1929(昭和4年) | |||
| 5.25 | 『台高新聞』創刊。比較文学で有名な文学者島田謹ニが英語科教授として就任 | ||
| 6.30 | 「講堂」(現礼堂)と古亭本部の七星寮(現存せず)竣工 | ||
| 10.1 | 「自由の鐘」本館屋上に設置 | ||
| 10.25 | 「プール」(現存せず)竣工 | ||
| 11.30 | 『次郎物語』の下村湖人(下村虎六郎)が第三代校長に就任。ニ度のストライキ事件に遭う | ||
| 1930(昭和5年) | |||
| 9.10 | 高等科生ストライキ | ||
| 11.15 | 「三澤糾先生の像」完成 | ||
| 1931(昭和6年) | |||
| 9.12 | 谷本清心が第四代校長に就任 | ||
| 1933(昭和8年) | |||
| 5.20 | 第6回寮祭開幕。新振り付けによる「台高踊り」披露 | ||
| 1936(昭和11年) | |||
| 1.1 | 全国高校ホッケ-で初優勝 | ||
| 1937(昭和12年) | |||
| 2月 | 新聞部より『台高』発行。『裏切られた台湾』の著者ジョ-ジ・カ-( GeorgeH.Kerr)が講師として就任 | ||
| 1941(昭和16年) | |||
| 8.26 | 下川履信が第五代校長に就任。前総統李登輝が入学。 | ||
| 12月 | 太平洋戦争勃発。軍事訓練のため、全校新店に行軍 | ||
| 1942(昭和17年) | |||
| 3.30 | 修業年限を短縮。万葉集研究の第一人者犬養孝が国語科教授として就任 | ||
| 1943(昭和18年) | |||
| 10月 | 文科生の徴兵猶予停止 | ||
| 1945(昭和20年) | |||
| 3月 | 全校の教師生徒が応召、13862部隊を編成し、淡水、大屯山等に駐屯 | ||
| 8.15 | 本日無条件降伏。全校の召集解除 | ||
| 9.10 | 授業再開 | ||
| 12. | 中華民国政府の接収により、「台湾省立台北高級中学」と改称 | ||
| 1946(民國35年) | |||
| 6月 | 「台湾省立師範学院」設立。台北高級中学と本学において共存 | ||
| 1949(民國38年) | |||
| 4月 | 台湾省立師範学院で「四六事件」発生。 | ||
| 7月 | 台北高級中学、最後の卒業生を送り出し閉校。全ての校舎や設備及び図書を省立師範学院が継承し、現在に至る | ||